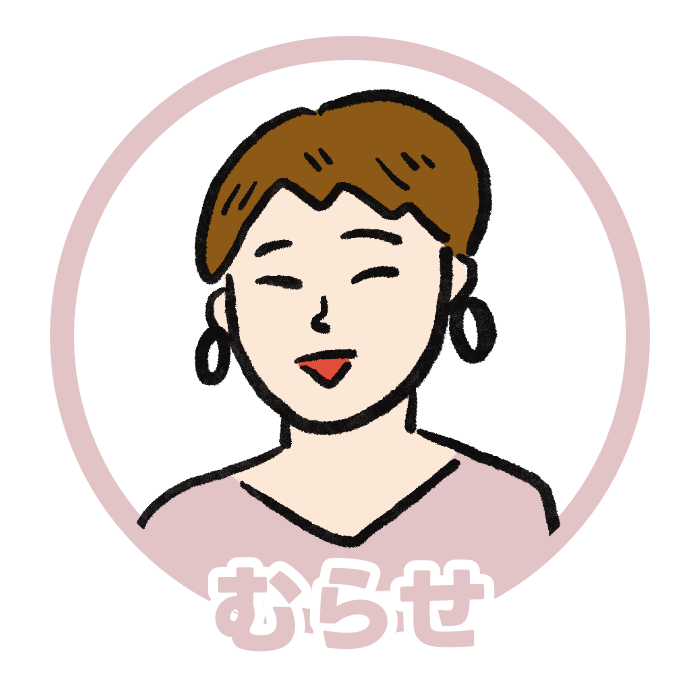よくも悪くもオンラインで仕事ができてしまうWEBクリエイター、マーケターのみなさん!「そういえば今日だれとも話してないな…」みたいなフリーランスの方!
飲みニケーション足りてますか?
われわれへノブスタッフもほぼリモートワークなので、週に1度の出社日は女子校の教室かよ😇というくらいおしゃべりが止まりません。
今回はWEBデザイナー、コーダー、WEBエンジニアなどのWEB制作に携わる(携わりたい)方を集めて、「交流会」という名の元、みんなでワイワイ飲みたいと思います〜
※安心してください!もちろん、お酒を飲まない方も大歓迎です◎
スナックうきしまとは?
WEB業界の片隅で20年… 独自進化を遂げたガラパゴス諸島の如く、 ぽっかり浮かぶへノブファクトリーが主催する交流イベントです。 スナックに集うような感覚で、肩肘張らずにゆるりと交流できる場を目指しています。

株式会社へノブファクトリーついて(普段はマジメに仕事をしています)
2004年創業、WEB業界21年目を迎えるWEBコンサルティング会社です。 創業当初はいわゆる一般的なWEB制作会社でしたが、自社ECサイト運営で培った戦略的売上UPのノウハウをベースに現在は「提案だけのコンサル会社」でも「作るだけの制作会社」でもない、「WEBで成果を出す専門家」として企業さまのWEB戦略〜実行までをご支援しています。
こんな方のご参加をお待ちしております
- WEB制作・WEBマーケティング業界に従事されている方
- へノブファクトリーの制作パートナー様
- これからWEB業界で働きたいと思っている方
- 気軽に参加できるWEB業界交流会を探している方
- フリーランスでお仕事をしている方
イベント詳細
株式会社ヘノブファクトリー主催! 参加者同士で自由に語り合える、WEB業界交流会的な飲み会イベントです。
WEB業界での人脈を広げたり、情報交換の場として活用いただけたら嬉しいです! また、WEBのお悩み・お仕事のご相談等もお気軽にどうぞ。カジュアルなイベントですので、どうぞみなさまお誘い合わせの上ご参加くださいませ!
<日時>
2026/02/19(木)18:00〜22:00 (開場17:50)
<会場>

リノスぺkitchen代々木
(東京都渋谷区 代々木1-42-7 不二ビル2F)
・小田急線 南新宿駅 徒歩2分
・JR山手線 代々木駅 徒歩3分
・東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩10分
<募集人数>
10名程度
<参加費>現地にて現金でお支払いください。
1,500円(2ドリンク付き & 乾き物フリー)
※3ドリンク目からはキャッシュオン